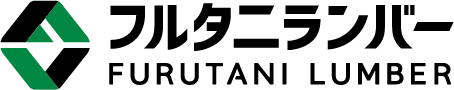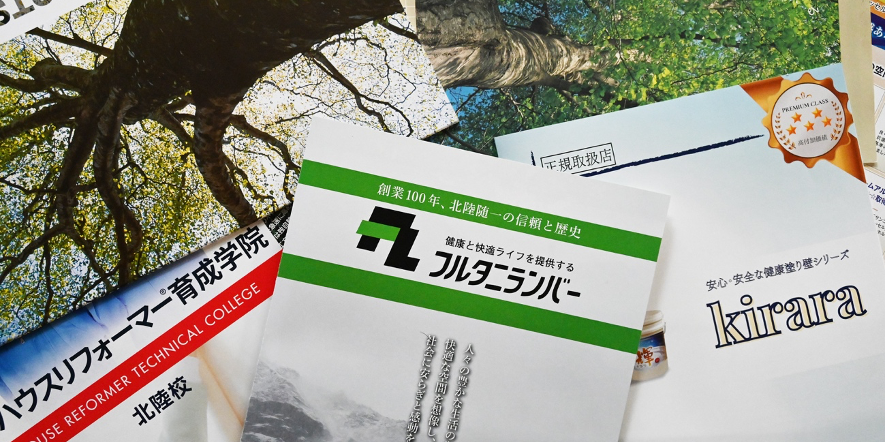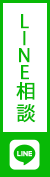フルタニランバー株式会社
コラム「森のフルタニさん」
無垢フローリング選びで後悔しないためのポイントを解説
投稿日:2025.04.01/更新日:2025.04.01

フローリング材は内装の印象を大きく左右する重要な存在であるため、高級感のある住宅に仕上げるためには特にこだわりたいポイントです。
中でも無垢フローリングは高い質感と木材本来の美しい色合いが魅力で、樹種によっても特徴が異なります。
そこで本記事では、無垢フローリングの主な樹種や特徴、選び方のポイントなどを詳しく解説します。
Contents
無垢フローリングとは?

無垢フローリングとは、天然の木材から一枚板切り出し、床材として加工したものを指します。
無垢フローリングの基礎知識として押さえておきたい内容をご紹介します。
無垢フローリングの基本的な特徴
無垢フローリングの最大の特徴は、木材本来の美しい見た目や質感が挙げられます。
丸太から一枚板を切り出しているためそれぞれに個性があり、高級感や特別感も感じられます。
また、使用する木材によっては、時間の経過とともに鮮やかな色合いから深みのある色合いに変化していくため、経年変化を楽しめるのも大きなポイントといえるでしょう。
一方で、天然の素材を贅沢に使用しているため床材の中でもコストが高く、メンテナンスの手間がかかるという側面もあります。
複合フローリングとの違い
無垢フローリングと混同しやすい床材に複合フローリングがあります。
木材を使用しているという点では共通していますが、複合フローリングは数mm程度の薄い板を複数枚重ねて作られます。
無垢フローリングに比べて安価な製品が多く、コストを抑えたい場合にはおすすめです。
また、複合フローリングの表面には防水加工や防汚加工が施されたシートやシールが貼られているものも多いため、メンテナンスもしやすい特徴があります。
関連記事:無垢板とは?メリット・デメリットから活用法まで紹介
無垢フローリングの種類とそれぞれの特徴

一口に無垢フローリングといっても、原料となる木材は針葉樹と広葉樹に大別され、樹種によっても特徴が異なります。
代表的な樹種と特徴をご紹介しましょう。
オーク(ナラ材)
オークは広葉樹の一種で、日本ではナラ材ともよばれます。
非常に密度が高く硬い木材であることから、耐久性が求められる無垢フローリングに用いられることが多くあります。
また、オークには害虫を寄せ付けないタンニンとよばれる成分が含まれているため、虫食いの被害を抑えられる点も大きなメリットといえるでしょう。
関連記事:オーク材とはどんな木材?特徴やメリット、使われる家具を紹介
パイン(松材)
パインは松材ともよばれ、日本でも馴染みのある針葉樹の木材です。
一般的にパイン材は海岸原産のレッドパインを加工したものを指し、国産のアカマツやカラマツなどは松材と表記されることもあります。
オークに比べると白みがかった鮮やかな色が特徴で、時間の経過とともに濃い褐色に変化していきます。
関連記事:パイン材とはどんな木材?経年変化や使用される家具、メリット・デメリットを解説
ウォールナット(クルミ材)
ウォールナットは広葉樹の一種であるクルミを加工した木材です。
主に北米から輸入されており、こげ茶色の深みのある色合いが特徴です。
ライフルなどの銃床に用いられるほど衝撃に強い特性があるため、耐久性が求められる無垢フローリングには最適な材料のひとつです。
ただし、ウォールナットは高級木材としても知られており、無垢フローリングの中でも特にコストがかかります。
関連記事:ウォールナット材とはどんな木材?経年変化や色、使用される家具について
チェリー(桜材)
チェリーは広葉樹の一種であるサクラのことで、北米から輸入されるブラックチェリー材やアメリカンチェリー材を総称してよばれることがあります。
表面が滑らかで鮮やかな色が見られるため、フローリング材以外にも高級家具や壁材としても用いられます。
無垢フローリングの中では比較的柔らかい木材ではあるものの、加工性に優れており温度や湿度による変形もしにくいメリットがあります。
関連記事:桜の木とは?サクラ材はどんな木材?特徴や値段について解説!
無垢フローリングを選ぶメリット

さまざまな床材がある中で、無垢フローリングを選ぶことでどのようなメリットが期待できるのでしょうか。
天然の温かみと保温性の高さ
木材は内部に空気を含んでいるため熱を伝えにくく、保温性に優れており冬場でも冷たさを感じにくい特性があります。
特に無垢フローリングは天然木ならではの温もりがあり、床暖房と併用することで、より快適な住環境を実現できます。
また、人工的なフローリングとは異なり、無垢材ならではの肌触りの良さも大きな魅力。
自然の温かみが感じられ、リラックスできる空間を作り出します。
調湿性の高さ
天然の木材は湿度を吸収・放出する調湿機能を備えており、室内の湿度を一定に保つ効果があります。
たとえば、高温多湿の夏場は余分な湿気を吸収し、乾燥する冬場には蓄えた水分を放出するため、快適な環境を維持しやすくなります。
また、湿度を抑えられることでカビやダニの発生を抑える効果もあり、健康的な住まい作りにも適しています。
クッション性と柔らかさ
無垢フローリングは適度な弾力性も持ち合わせているため、歩いたときの衝撃を和らげる効果があります。
長時間立っていても足腰への負担が少なく、キッチンなどの立ち仕事が多い場所にも適しているでしょう。
木材の種類によっても硬さは異なりますが、パインやチェリーなど比較的柔らかい樹種を選べば、足腰の機能が低下した高齢者でも快適な住環境が実現できます。
自然な美しさと経年変化
無垢フローリングは天然木ならではの美しさが魅力で、木目や節が一枚ごとに異なり個性を楽しめます。
また、経年変化によって色合いが深まり、年月とともに味わいが増していくのも特徴です。
使い込むほどに深みとツヤが出るため、新品の時とは違った表情を見せてくれるのも無垢材ならではの楽しみ方です。
含有する化学物質の少なさ
無垢フローリングは接着剤や化学薬品をほとんど使用せずに作られるため、有害物質の影響が少ないのが特徴です。
特に、小さな子どもやアレルギーを持つ人など、安全性を第一に考えたい場合には最適な素材といえるでしょう。
また、天然の木材が放つ独特の香りにはリラックス効果があり、心身ともに落ち着ける空間も実現します。
無垢フローリングのデメリットと注意点

無垢フローリングは天然の木材をそのまま使用しているため、デメリットや注意すべき点もあります。
水に弱い
無垢材は水分を吸収しやすい弱点があるため、水濡れには注意が必要です。
無垢フローリングの中に水が染み込むと、シミや変色の原因となるだけでなく、膨張して床材が変形することもあります。
特にキッチンや洗面所などの水回りに施工する際には、防水対策を施したり、水が付着した際にはこまめに拭き取ることが大切です。
傷が付きやすい
無垢フローリングは合板や複合フローリングに比べると適度な柔らかさがあるため、強い衝撃や力が加わるとダメージを受けやすくなります。
たとえば、家具の移動や物の落下、ペットによる爪の引っかきは傷が付きやすいため注意が必要です。
傷が気になる場合は、フローリングと直接家具の間にクッションやカバーを挟めたり、ペットが行き来する場所にはラグやカーペットを敷くなどの対策を施しましょう。
膨張・収縮による変形
無垢フローリングは湿度や気温の変化に応じて膨張・収縮しやすい性質があります。
特に梅雨時や冬場の乾燥期には木材が伸縮しやすく、床材の隙間が広がったり、反りや割れが発生することも少なくありません。
そのため、加湿器や除湿機をうまく活用し、年間を通じて室内の湿度を40~60%に保つことで無垢材の変形を最小限に抑えることができます。
施工コストが高い
無垢フローリングは一般的な合板フローリングに比べて価格が高く、施工にも高度な技術が求められます。
木材の種類によっても価格差があるほか、材料費だけでなく工賃や施工費も考慮しておく必要があります。
予算を抑えたい場合には、たとえば部分的に無垢材を取り入れるなどの工夫をすると良いでしょう。
メンテナンスが必要
無垢フローリングの美しさを維持するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。
たとえば、表面が乾燥しすぎるとひび割れのリスクが高まるため、オイル仕上げの無垢材の場合は定期的にオイルやワックスを塗布する必要があります。
手間はかかりますがその分愛着が湧き、経年変化を楽しみながら長く使えるのが無垢フローリングの魅力でもあります。
無垢フローリング選びで後悔しないためのポイント

無垢フローリングにはさまざまな種類があるため、選び方を間違ってしまうと後悔する可能性もあります。
どういった点に注意すべきなのか、後悔しないためのポイントをいくつかご紹介します。
樹種の特性を理解して選ぶ
無垢フローリングにはさまざまな樹種があり、それぞれ硬さや色合い、木目の雰囲気が異なります。
たとえば、パインやチェリーは柔らかくクッション性に優れている反面、傷が付きやすいという弱点があります。
また、オークやウォールナットは深みのある色合いが特徴的で、重厚な雰囲気の部屋に仕上がります。
事前にそれぞれの特性を理解し、見た目はもちろんのことライフスタイルに合った木材を選ぶことが重要です。
用途に応じて選ぶ
無垢フローリングは使用する部屋や環境に合わせて選ぶことも大切です。
たとえば、リビングや寝室は柔らかく肌触りの良いパインなどの木材が適していますが、水回りや玄関など汚れが付きやすい場所では、耐水性のあるウォールナットやウレタン塗装仕上げのものが向いています。
塗装方法で選ぶ
無垢フローリングには主に「オイル塗装」「ウレタン塗装」「無塗装」の3種類の仕上げ方法があり、それぞれ特徴が異なります。
- オイル塗装:木の質感を活かせるが、定期的なメンテナンスが必要
- ウレタン塗装:防汚効果と耐水性に優れメンテナンスが楽だが、木の自然な風合いは損なわれる
- 無塗装:無垢材本来の質感を楽しめるが、汚れが付着しやすく耐久性が低下する
仕上げの特徴を理解し、使用する場所に応じて適したものを選びましょう。
床暖房の有無を考慮する
無垢フローリングの中には、床暖房に対応していないものもあるため事前に確認が必要です。
木材は熱による影響を受けやすく膨張・収縮を繰り返すため、床暖房に適した加工が施されていない無垢材を使用すると、反りや割れの原因になります。
施工時点で床暖房を導入していなかったとしても、今後導入する可能性があるかも考慮しておきましょう。
実物を確認する
無垢フローリングはカタログやWebサイトに掲載されている画像を参考に選ぶケースがほとんどです。
しかし、実物を確認してみるとイメージしていた質感や色合いとは異なって見えることも少なくありません。
このように、写真やカタログだけでは質感や色合いを正確に把握するのが難しいため、できるだけ実物を確認することが重要です。
また、施工後の経年変化も考慮し、時間が経つとどのように色合いが変化するのかを確認しておくと、イメージとのギャップを防ぐことができるでしょう。
関連記事:家具や木造住宅に使用される人気の木材の種類一覧やそれぞれの特徴
無垢フローリングのお手入れ方法と長持ちさせるコツ

無垢フローリングを長持ちさせるためには、日頃からこまめなメンテナンスが不可欠です。
正しいお手入れの方法と長持ちさせるためのコツをご紹介しましょう。
月1~2回の水拭き
無垢フローリングは水を吸収しやすい特性があるため、日常的なお手入れは基本的に乾拭きがおすすめです。
ただし、汚れがひどい場合や油汚れなどが気になるときは、固く絞った布で月1~2回程度の水拭きを行いましょう。
水拭き後は必ず乾いた布で仕上げ拭きをし、余分な水分を残さないことがポイントです。
年1~2回のワックスがけ
無垢フローリングを長持ちさせるためには、年に1〜2回程度の定期的なワックスがけが重要です。
ワックスを塗ることで表面に保護膜ができ、汚れや傷、水分の浸透を防ぐ効果が期待できます。
ただし、ウレタン塗装の無垢フローリングは表面に樹脂コーティングが施された状態になっているため、基本的にワックスがけは不要とされています。
もし表面のツヤやコーティングの剥がれが気になる場合には、メーカーや施工会社に正しい対処法を確認しておきましょう。
塗布する際は専用の無垢フローリング用ワックスを使用し、薄く均一に塗ることがポイントです。
また、ワックスがけの前にはしっかりと汚れを落としておくことで、ムラのない仕上がりが期待できます。
オイル塗料での再塗装
オイル仕上げの無垢フローリングは、年に1回程度オイル塗装を行うことで美しい質感を維持できます。
オイル塗装は木材に浸透して内部から保護するため、自然な風合いを損なわずにメンテナンスできるのが特徴です。
オイルを塗る前には表面の汚れをしっかり落とし、必要に応じて軽く研磨すると均一に塗布できます。
まとめ
天然の木材がもつ美しい風合いと質感を楽しめる無垢フローリング。
樹種によっても硬さや色合い、質感が異なるため、複数の製品を比較しながら理想的な床材を見つけることが大切です。
石川県金沢市にある木材販売会社フルタニランバーでは、さまざまな無垢フローリング材を取り扱っているため、まずはお気軽にご相談ください。