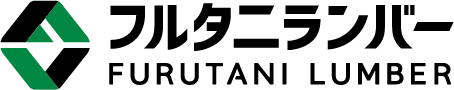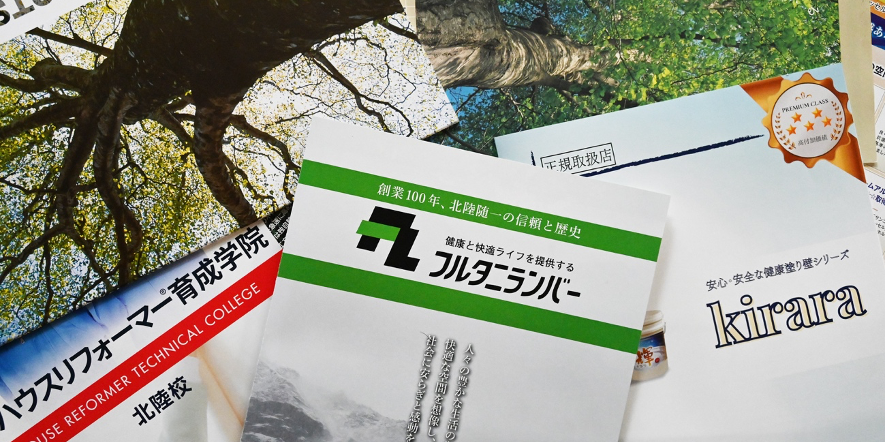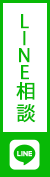フルタニランバー株式会社
コラム「森のフルタニさん」
米ヒバ(ベイヒバ)とは?木材としての特徴や価格を徹底解説
投稿日:2024.03.10/更新日:2024.04.03
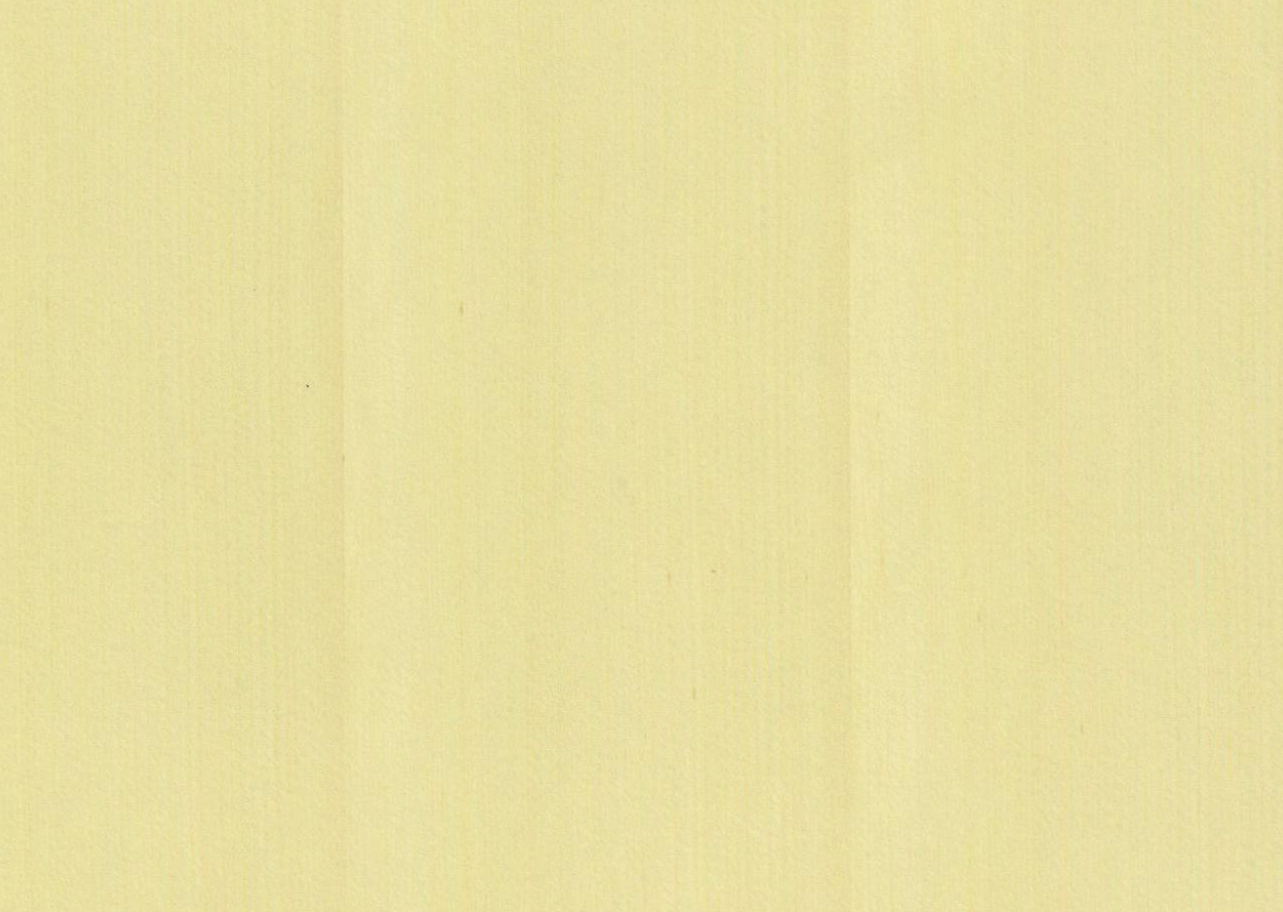
安価で機能性に優れた木材はさまざまなものがありますが、なかでも代表的な木材として挙げられるのが米ヒバです。
その名の通りアメリカ産の輸入木材ですが、日本では古くから建材や家具材などに幅広く用いられてきました。
本記事では、米ヒバとはどういった木材なのか、主な特徴を紹介するとともに、国産のヒバ材との違いや価格相場なども徹底解説していきます。
Contents
米ヒバ(ベイヒバ)とは

米ヒバとは、ヒノキ科ヒノキ属の常緑針葉樹です。
「米」という名がつく通り、主な原産地はカナダとアメリカで、特に太平洋側の西海岸沿いに位置するアラスカ州からオレゴン州の標高の高い山で採取されます。
ヒノキ科であるにもかかわらず「ヒバ」という名前がついているのは、加工した際に国産のヒバに似た独特の香りを放つためです。
なお、日本国内では米ヒバという名称が一般的ですが、正式名称は「イエローシーダー」で、ほかにも「アラスカヒノキ」や「アラスカシーダー」とよばれることもあります。
関連記事:ヒノキ(檜・桧)の木材の特徴や原木価格|ヒバとの違いについても
米ヒバ(ベイヒバ)の木材としての特徴

米ヒバはさまざまな用途に使用される木材です。木材として加工・使用するにあたって、どのような特徴が見られるのでしょうか。
柔軟で加工しやすい
米ヒバは木材そのものが柔らかく、また木目も真っ直ぐに通っているため加工がしやすい特徴があります。
木工作業に慣れていない方でも工具で比較的簡単にカットできるため、DIYにも人気の木材です。
腐朽性に優れる
米ヒバが放つ独特の臭気には、セドロールやヒノキチオール、カルバクロールといった害虫が嫌う成分が多く含まれています。
木材にとっての天敵ともいえるシロアリを寄せ付けない効果があるため、優れた耐腐朽性を発揮します。
防湿性が高い
米ヒバのもう一つの強みとして、防湿性が高いことも挙げられます。
湿度が高い場所や水に濡れやすい場所に置いても腐食することが少なく、優れた耐久性を維持してくれます。
関連記事:桜の木とは?サクラ材はどんな木材?特徴や値段について解説!
米ヒバ(ベイヒバ)の用途

上記でも紹介した通り、米ヒバは柔軟で加工がしやすく、腐朽性や防湿性にも優れていることからさまざまな用途に使用されています。
主な用途をいくつかご紹介しましょう。
構造材
建築で使用される建材は米ヒバの代表的な用途です。
特に米ヒバは腐朽性と防湿性に優れていることから、柱や土台といった構造材に使用されることが多くあります。
柱や土台は建物を支える特に重要な部分であることから、米ヒバを使用することでシロアリや腐食を防ぎ、建物の耐久性を高められるメリットが期待できるのです。
内装材
同じく建築の分野で用いられることが多いのが、壁や床、天井などに施される内装材です。
米ヒバは木の香りが強く、内装材に用いることで上質な雰囲気と安心感を感じられます。
また、米ヒバの木目は均一で直線的なほか、木肌も鮮やかな黄白色をしているため、内装材として使用することで目で楽しめる点も大きな魅力といえるでしょう。
家具・建具
家具・建具の材料としても、米ヒバは多く用いられます。
特に害虫の忌避効果を活かしてタンスや小物入れ、衣装ケースなどの材料になることが多いです。
柾目の美しい板は建具としても活用されます。石川県では塗の下地材としても使われます。
また、優れた防湿性を活かし、浴室の椅子や風呂蓋といった小型家具や雑貨にも使用されることがあります。
船舶
現在の船舶は、安全性の観点から鉄などの金属によって造られていますが、一部の小型船や伝統的な屋形船などは木材が使用されています。
つねに水面に接しているという船の特性上、腐食や水に強い米ヒバが材料として用いられることが多くあります。
木型
木型とは、鋳物を製造する際に用いられる模型のようなものです。
鋳物は鋳型とよばれるものに金属を流し込んで作られますが、この鋳型を作るためには設計図から模型のようなものを作らなければなりません。
そこで、柔らかい木材である米ヒバを削り、製品の原型ともいえる木型を作っていきます。
楽器
米ヒバは太鼓のバチの材料として用いられることがあります。
直線的な木目でカットがしやすく、木材そのものが柔らかく適度なしなやかさがあるため、叩いたときの感触が良好です。
関連記事:ブナの木(ビーチ材・ブナ材)の特徴とは?経年変化やオーク材との違いを解説
米ヒバ(ベイヒバ)の価格

米ヒバは輸入木材として供給量が多いため、国産のヒバ材に比べると比較的安価で購入できます。
木材のサイズや長さによっても価格は異なりますが、大まかな相場は以下の通りです。
- 厚さ105mm×巾105mm×長さ4000mm:10,000円
- 厚さ90mm×巾90mm×長さ4000mm:8,000円
- 厚さ105mm×巾105mm×長さ2000mm:13,000円
- 厚さ105mm×巾105mm×長さ1000mm:1,800円
- 厚さ120mm×巾120mm×長さ1000mm:2,000円
上記は2024年3月時点での価格相場であり、供給量や為替の影響などによっても相場が変動することがあります。
関連記事:木材加工とはどんな加工?種類や機械、依頼する業者を選ぶポイント
米ヒバ(ベイヒバ)の香りの特徴
米ヒバは国産のヒバ材と似た、木独特の香りが感じられます。
特に丸太からカットした直後は強い香りを放ち、木材として加工した後は年数の経過とともに徐々に香りは薄くなっていきます。
また、上記でもご紹介した通り、米ヒバにはセドロールやヒノキチオール、カルバクロールなどの成分が含まれており、これらによって独特の匂いを感じることができます。
ただし、国産のヒバ材に比べると上記成分の含有量は少なく、匂いも全く同じというわけではありません。
米ヒバ(ベイヒバ)にデメリットはある?

供給量が多く、安価でありながらも木材としての機能も優れた米ヒバは、メリットばかりで欠点がないようにも感じられます。
しかし、米ヒバにも少なからずデメリットは存在します。
ヒバ材と同等の役割は期待できない
冒頭でもご紹介した通り、米ヒバは「ヒバ」という名前が付いていますがヒノキ科の樹木です。
シロアリや腐食、水に強いといった特徴はヒバ材と共通する部分ではありますが、全く同じ役割を果たせるものではありません。
特にヒノキチオールをはじめとした害虫の忌避成分は、米ヒバよりもヒバ材のほうが成分量が多く、木材としての特徴は共通していても効果が得られる程度や持続期間は異なります。
香りが苦手な人も
ヒバやヒノキに含まれる木独特の香りは、多くの人にとって心地良いと感じるものです。
しかし、中には木の香りが苦手な人や、新しい木材では香りがきつすぎて気分が悪くなるといった人もいます。
米ヒバを建具や内装材、家具などに使用する際には、それらを使用する人の体質を考慮することも大切です。
木材のご相談はフルタニランバーまで
米ヒバは供給量が多く、ホームセンターやネット通販などでも比較的手に入りやすい木材です。
しかし、用途によっては適合するサイズのものが見つからなかったり、品質に不安を感じたりすることもあるでしょう。
そのような場合には、石川県の木材販売会社フルタニランバーまでご相談ください。
海外の現地工場からの直接仕入れと検品、大量在庫を確保することにより、高品質と低価格を両立しています。
また、フルタニランバーでは無垢板材や集成材、床材、合板などさまざまな木材を取り扱っており、用途に応じてオーダーメイドでの加工にも対応できます。